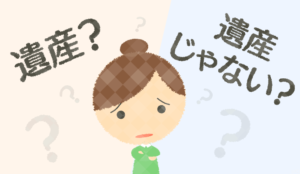【判例変更に注意!】嫡出子・非嫡出子の相続分について
「嫡出子と非嫡出子の相続分が変更になったって聞いたけど」
子供の相続分は昔から平等だと思いますよね。実は、ここ最近まで子供の相続分が平等ではなかったんです。
今回は、平成25年9月に変更になった子供の相続分について、今後の遺産分割協議への影響も含めて解説します。
嫡出子・非嫡出子とは
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、結婚している男女間に生まれた子供のことをいいます。これに対して、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、結婚していない男女間に生まれた子供のことをいいます。
嫡出子・非嫡出子の不平等が解消された
かつての非嫡出子の相続分は半分だった
非嫡出子の相続分はかつて、嫡出子の半分とされていました。
相続人が妻と長男Aと次男Bの3名という具体的に例でご説明します。長男、次男ともに嫡出子であれば法定相続分は、妻が2分の1、長男、次男がそれぞれ4分の1ずつとなります。しかし、もし次男が非嫡出子であったなら、長男の半分の相続分しかないので、法定相続分は妻は変わらず2分の1、長男6分の2、次男は6分の1となります。
結婚していない男女の間に生まれたというだけで、相続分に大きな差があったのです。
かつての判例
最高裁は長らく、婚姻届を出して正式に婚姻関係がある夫婦の間に生まれてきた子どもを尊重しようと考えていました。そのため、婚姻関係にある男女から生まれた子を、婚姻関係にない男女から生まれた子より優先して考えていたのです。
しかしこれは法の下の平等(憲法14条1項)に違反するのでは?という議論が昔からありました。
判例が変わった
最高裁は平成25年9月4日の大法廷決定で、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差をつけた規定は法の下の平等に違反するとして、今までの判例を変更したのです。それには、国民の意識などの変化があった為だと言われています。
つまり、事実婚が増えてきたことや家族の在り方が多様になってきたこと、子供は何も関係ないのに生まれながらにして法定相続分が少ないのはおかしいなどが理由です。その結果、嫡出子も非嫡出子も同じ法定相続分となりました。
今までの遺産分割協議はどうする
平成25年9月4日までに整った遺産分割協議については影響はありません。さすがに昔の遺産分割協議までも変更することになったら、みなさん大混乱してしまうので、すでに決まっている協議はそのままです。
しかし、平成25年9月4日以降に協議するものについては、嫡出子と非嫡出子の法定相続分が同じであることを前提に話し合いをしなければなりません。
まとめ
以前は、結婚している夫婦の間の子供を尊重しようと前述のように相続分に差を設けていました。ただ、近年はライフスタイルの変化や家族の在り方が多様にになってきたため、その世論が今回の判例変更に繋がったのではないでしょうか。
これから遺産分割協議をするときは、この判例を参考に嫡出子と非嫡出子の相続分を平等にして計算しましょう。