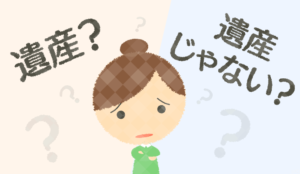相続があった時、相続人になれる養子となれない養子
「養子も相続人になれるの?」
養子の制度は、節税のためや子供の福祉のためなどの目的で、利用している方が多いのではないでしょうか?
逆に、今から養子の制度を利用したいと思っている方は、基本的なことを知っていないと利用したくても利用できませんよね。
そこでこちらでは、2つの養子制度についてご説明します。
養子縁組の種類
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つの種類があります。
普通養子縁組とは
普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)とは、養子が実親との親子関係を残したまま養親と法律上の親子関係を作り出すものです。つまり、実親との縁は切らないのです。
普通養子縁組は、再婚の際の連れ子を相続人にする為に利用したり、または相続税対策でも利用されたりします。
普通養子縁組は養子になる者の福祉や保護以外の理由からも利用される制度です。
特別養子縁組とは
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、養子が実親との親子関係を断ち切り養親との親子関係を作り出すものです。つまり実親との縁は切れます。
実親との縁が切れるという重大な効果が生じる為、特別養子縁組は実親による監護が著しく困難又は不適当などの特別な事情がなければなりません。
特別養子縁組の制度は、養子になる者の保護や福祉のために利用される制度なのです。
普通養子縁組と特別養子縁組の比較表
分かりにくい普通養子縁組と特別養子縁組を下記の表にまとめてみました。
特に制度の違いが分かるのは、「養子の目的」「養親になる要件」「養子の要件」の個所です。
例えば普通養子縁組の場合、縁組をする目的に条件はありません。つまり、相続税対策や家業を守るために養子縁組をするなど、私的な理由でも制度を使えるのです。それに比べ特別養子縁組は、子どもの福祉のためでないと制度を利用できません。また特別養子縁組は、養親になる人や養子になる人にも年齢制限があり、要件が厳しくなっていることが下記の表からも分かります。
それは、特別養子縁組が養子になる子の福祉のための制度であるからです。
| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
|---|---|---|
| 養子の目的 | 特に条件はなし | 子どもの福祉を図るため |
| 養親になる要件 | 成人であること | 満25歳以上で婚姻している夫婦であること |
| 養子の要件 | 養親よりも年下 | 原則、満6歳未満 |
| 養子縁組の手続き | 原則、当事者から役所への届出 | 家庭裁判所の審判 |
| 実親等の同意 | 養子が15歳未満のときは、法定代理人の承諾が必要 | 実の父母の同意が必要 |
| 親子関係 | 実の親子関係は継続する | 実の親子関係は終了する |
| 戸籍の記載 | 養子と記載される | 養子と記載されない |
| 離縁 | 当事者の協議で可能 | 家庭裁判所の審判が必要 |
| 相続順位 | 第1順位(実子と同じ) | |
| 法定相続人 | 実の父母、養親の両方の相続人となる | 養親のみの相続人となる |
まとめ
前述の通り、普通養子縁組の場合は実の親との関係は継続します。そのため養子になったからといっても、実の親の相続人になることが出来ます。
しかし特別養子縁組の場合は、実の親との関係は終了しますので、実の親の相続人にはなれません。養親のみの相続人になるのです。相続人を確定させるときは注意が必要です。